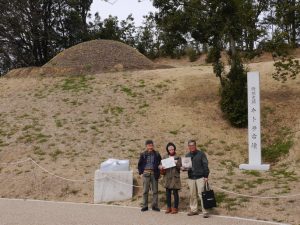第30回さるく会は「歴史遺産と琵琶湖畔・大津さるく」です。 大津は、京都に近いこともあり、昔から人や物が往来する交通の要衝として栄えてきたところです。
今回は、大津にある重要文化財や国指定史跡等々を巡り、シバサクラが咲く琵琶湖畔を散策します。その他にも競馬の馬主達が祈願に訪れるという馬神神社や忘れられた大津城跡、昔の人が通った東海道など知らなかった大津を再発見できると思います。ぜひご参加ください。(21回生 鳥山記)
見どころを紹介いたします。
<義仲寺 (ぎちゅうじ) >
粟津(あわづ)の地で壮烈な最期を遂げた木曽義仲(室町時代末期に葬ったといわれています。江戸時代中期までは小さな塚でしたが、周辺の美しい景観をこよなく愛した松尾芭蕉が度々訪れ、のちに芭蕉が大阪で亡くなったときは、生前の遺言によってここに墓が立てられました。境内には、芭蕉の辞世の句や直筆の句碑など数多くの句碑が立ち、偉大な俳跡として多くの人が訪れます。境内全域が国の史跡に指定されていますが、特に、翁堂の天井画は、伊藤若冲が描いたと言われており、必見の価値があります。
<なぎさ公園のシバザクラ>
においの浜にある、なぎさ公園「なぎさのプロムナード」エリアには花壇一面にシバザクラが咲き誇ります。琵琶湖の青とのコントラストも美しく、湖岸散策を楽しむ市民や観光客に親しまれています。
<大津城跡>
安土・桃山時代に、豊臣秀吉が、坂本城にかわり、新たに大津城を築城しました。関ケ原の戦で、東軍(徳川家康側)に味方した城主の京極高次が、関ヶ原に向かう毛利元康の大軍を食い止めて時間稼ぎをしたという「大津籠城」は、勝敗を決める大きな要素となったことで有名です。徳川家康(1541-1616)が大津城で戦後処理を行ったこともよく知られています。この後廃城となり城は解体されましたが、城郭の資材は、彦根城や膳所城の築城に使われたといわれています。
<琵琶湖疏水>
京都への飲料水の供給と灌漑、水運、発電を目的として約5年の歳月をかけて明治23年(1890)4月に完成しました(第2疏水は明治45年(1912)に完成、全線トンネルで、延長7.4km)。全長11.1km、日本人だけの技術で、資材面などの困難を克服し、明治中期における日本土木技術の確立を示す画期的な事業といわれます。
<三井寺>
天台寺門宗の総本山で「長等山園城寺」と言います。境内に天智・天武・持統の三天皇の御産湯に用いられたとされる霊泉(井戸)があることから、「御井(みい)の寺」と称され、後に「三井寺」と通称されるようになりました。国宝の金堂を始め、西国第十四番札所の観音堂、釈迦堂、唐院など多くの堂舎が建ち並び、国宝・重要文化財は一〇〇余点を数えます。その他のみどころとしては、近江八景「三井晩鐘」や弁慶の引摺り鐘などがあります。
<大津事件の碑>
明治24年(1891)、来日したロシア皇太子ニコライが、警備中の巡査津田三蔵に斬りつけられた事件。ロシアを恐れる明治政府は、津田三蔵を大逆罪で死刑にするよう迫りましたが、 大審院長の児島惟謙の主張により、刑法どおり無期徒刑とし、司法権の独立を貫きました。 事件現場には、「此附近露国皇太子遭難之地」の碑が建っています。
【ご参考】
ゴールデンウィークも今日で終了。現役の方は明日からは仕事。大変ですね!一方おじいちゃん・おばあちゃんはほっとされている方も。ところで今回試しに長崎絡みの番組を紹介したいと思います。下記番組ですが懐かしい「東洋軒のサラダパン」が登場します。お店は変わっていますがその味を引き継いだパンとか!?一度ご覧になってみてください。(もし間違ってたらごめんなさい)
◆日時:5月8日(月)23:00~23:30(30分)
◆チャンネル:NHK BSプレミアム(Ch.3)
◆番組詳細:今回の舞台は、長崎県。カステラやちゃんぽんが有名だが、実は出島を中心に早くから西洋のパン文化が根づく土地。地元の人たちに大人気の独特の「ご当地パン」がたくさん作られている。木南晴夏と旅をするパートナーは、長崎県出身のHKT48・森保まどか。長崎県を縦断して地元で愛されている珍しいご当地パンを探す。そこでしか味わえない極上パンを堪能し、長崎県のパン文化の魅力に迫る!
19回生の同期会「関西トーク会」を下記のとおり実施します。たくさんの参加をお待ちしております。
【青蓮院門跡青龍殿・大舞台見学】
◆日時:平成29年4月19日(水) 10時30分~
◆集合場所:三条京阪駅B1F 中央改札口を出た付近
◆会費:女子 5,500円,男子 7,000円(拝観料、タクシー代、懇親会費含む)
※青龍殿・大舞台見学後、タクシーで懇親会場の京都つゆしゃぶCHIRIRI(ちりり)へ移動、懇親会から参加の2人と合流します。
【懇親会】
◆日時:平成29年4月19日(水) 12時~
◆場所:京都つゆしゃぶCHIRIRI(ちりり)
京都市上京区室町通丸太町上ル大門町265
075-222-5557
http://www.chiriri.co.jp/kyoto/
◆懇親会のみの会費:5,500円
第30回関西さるく会「滋賀大津 琵琶湖畔さるく」を実施します。春のうららかな琵琶湖の湖畔をさるいてみませんか。
◆日時:4月23日(日) 10:00集合 10:15出発
◆集合場所:JR膳所駅
◆コース:膳所駅~義仲寺~においの浜~大津城跡~琵琶湖疎水~三井寺~大津事件碑~JR大津駅(約6㎞)
※詳細は追って連絡します
◆参加自由。雨天決行。連絡不要。家族参加大歓迎。弁当持参。 レクリェーション保険加入。 気軽に参加できる同窓会活動です。
さるく会、18才の君がいる、僕がいる!
第26回常任幹事会を下記のとおり実施します。今回は会議に先立ち「同窓会だより」第5号の封入作業を行います。常任幹事の方はご出席のほどよろしくお願いいたします。
<同窓会だより封入作業>
◆日時:4月15日(土)13:00~15:00
<常任幹事会>
◆日時:4月15日(土)15:00~17:00
◆場所:いずれも井戸本会計事務所
お待ちかねの第7回「関西ナイスショット&ファーの会」を下記内容で実施します。今回は世界遺産 法隆寺の近く「法隆寺カントリー倶楽部」での開催です。ふるってご参加ください。
◆日 時 : 4月1日(土) 9:27 スタート(セルフ) (集合は8:50の予定)
◆場 所 : 法隆寺カントリー倶楽部
奈良県生駒郡斑鳩町大字三井1052
TEL 0745-75-2551
http://www.pacificgolf.co.jp/horyuji
◆組 数 : 4組
◆プレー費: 16,000円(昼食付)
◆参 加 費 : 3,000円(パーティ費、景品等)
◆申込み : 組合せなどの調整のため、出席/欠席のご連絡を2月28日までに幹事林田までメールください。 なお幹事林田のメールアドレスをご存じない方は上段のボタン「お問合わせ/ご連絡」からご連絡いただくこともできます
※関西在住者以外の方も大歓迎です!たくさんの方の参加をお待ちしております。
関西同窓会の3番目の同好会となる写真クラブが発足します。
会のキャッチフレーズは「四季の素晴らしい風景や楽しいできごとをお気に入りの写真として残しませんか」。 そして会則にある通り「親睦と技術の向上、 四季と地域の再発見を目的とした活動」を目指します。ご期待ください。
詳しくは4月1日付の新着情報でご紹介します。
第30回滋賀大津 琵琶湖畔さるくの下見を実施します。今回も地域役員以外の方も参加できます。4月23日(日)のさるく会に参加できない方は奮って参加ください。
◆日時:4月1日(土) 10:00集合
◆集合場所:JR膳所駅
◆コース:膳所駅~義仲寺~においの浜~大津城跡~琵琶湖疎水~三井寺~大津事件碑~JR大津駅(約6㎞)
※地域役員以外の方は下記の通り通常のさるく会に準じた内容です。
◆会費:300円
◆参加自由。雨天決行。連絡不要。家族参加大歓迎。弁当持参。下見保険加入。
◆また今年から採用された「皆勤賞」の出席対象になります。
関西さるく会恒例のお花見を下記の要領で実施します。背割堤は全国的に有名な桜の名所です。はなとお酒と、そしておしゃべりで楽しいひとときを過ごしませんか。たくさんの参加をお待ちしています。(19回生 梅木記)
◆日時:4月2日(日) 10時集合
◆場所:京阪八幡市駅
◆花見の場所:背割堤 京都府八幡市八幡在応寺地先
◆その他:
連絡不要、会費無料、雨天実施、レクリェーション保険加入、
弁当とお酒持参(松花堂弁当3780円の希望者は3月29日までに梅木さん(090-8934-3759)に連絡)
※関西さるく会の皆勤賞の対象外です。
<背割堤のポイント>
桂川、宇治川、木津川は背割堤で三川合流し淀川となります。
歴史のひとコマとして、この地で千利休は茶の弟子細川幽斎に見送られ、川を下り、切腹の場所に赴いたというところでもあります。さもありらん、川はとうとうと流れ、舟はみるまもなく、闇に吸い込まれて行ったのでしょう。
ソメイヨシノは野生種、エドヒガンザクラとオオシマザクラの雑種なり。よって、基本的に種ができません。
だから、全国すべてのソメイヨシノは接ぎ木か挿し木でできたものです。いわゆるクローンです。ゆえにソメイヨシノの寿命はわりと短かい。吉野はヤマザクラですがその他は殆んどソメイヨシノです。
花は桜木、人は武士とうたわれた軍歌も桜はソメイヨシノ。この桜、お城のサクラや土手の上のサクラは立派です。かの地の土は盛り土にて、やわらかでかたくしまってません。水はけもいいです。
この条件にぴったりあうのが、背割堤です。かの地のソメイヨシノはいまや、全盛期かとおもわれます。関西の雄と言っても過言ではありません。
私達の故郷、ばってん長崎坂の町では桜の花見などあまりなかったようにおもいます。せいぜい、日見峠か大村公園だったでしょうか。日出ずる高校、天下に冠たる東高の同志と共に、この地で花見が出来るとは名誉の事なり。
そんな大げさなぁ~。
<もう一つお弁当について!>
近くに、京都吉兆、松花堂店があります。創業者、湯木氏、考案の松花堂あり、弁当もあります。私たちが区切られたお弁当を何気なくというか一般用語として使ってる、松花堂は江戸の文人、松花堂昭乗の種子、もみなど入れた小箱から湯木さんがつくたもんだったんですね。まあ、一度ご賞味しても、よかでしよう。御値段に合いましたら。税込み、3780円です。3月29日まで希望者は梅木まで連絡いただいたら、買い出し承ります。
お酒は各自、ご用意願います、駅にコンビニありますが、花見場所から、買いに行くのは不可能です。千鳥足では帰ってこれませんので、飲みたいと思うぶんや、同志に飲んで欲しいぶんはご持参願います。余ったら、千利休の送りに淀に流しましょう。
<雨天について>
雨天の時ですが、花も嵐も踏み越えてやります。傘とカッパをご用意願います。
19回生の梅木でした!

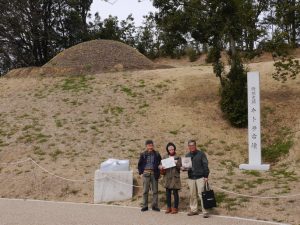




第29回は奈良県の高取土佐町雛めぐりさるくです。高取町は明日香のお隣の町。日本三大山城で有名な高取城の城下町です。その高取町土佐街道筋の町家100軒以上がお雛さまをそれぞれに展示します。御殿雛や稚児雛、そしてジャンボ雛などなど町内挙げてのおもてなしです。一見の価値あり!たくさんの参加を!
◆日時:2017年3月26日(日)10時集合 10時15分出発
◆場所:近鉄飛鳥駅
◆コース:近鉄飛鳥駅~檜隈寺跡~キトラ古墳(昼食)~高取土佐町(反省会)~近鉄壺阪山駅(6キロ)
◆アクセス:今回は遠いので10時2分到着の電車を案内します
◇大阪から:JR大阪 8:43発(環状線大和路快速奈良行)~JR天王寺着 8:59~(徒歩)~近鉄大阪阿倍野橋 9:20発(近鉄南大阪線急行吉野行)~近鉄飛鳥10:02着
◇京都から:近鉄京都 8:40発(近鉄京都線急行橿原神宮前行)~橿原神宮前 9:51着~橿原神宮前 9:58発(近鉄南大阪線吉野行)~近鉄飛鳥10:02着
もしもう少し早く着きたい方は
◇大阪から:JR大阪 8:17発(環状線西九条方面)~JR天王寺着 8:38~(徒歩)~近鉄阿倍野橋 8:50発(近鉄南大阪線急行吉野行)~近鉄飛鳥9:34着
◇京都から:近鉄京都 8:06発(近鉄京都線急行橿原神宮前行)~橿原神宮前 9:18着~橿原神宮前 9:30発(近鉄南大阪線吉野行)~近鉄飛鳥9:34着
◆会費:会費 300円
◆参加自由。雨天決行。連絡不要。家族参加大歓迎。弁当持参。 レクリェーション保険加入。 気軽に参加できる同窓会活動です。
さるく会、18才の君がいる、僕がいる!